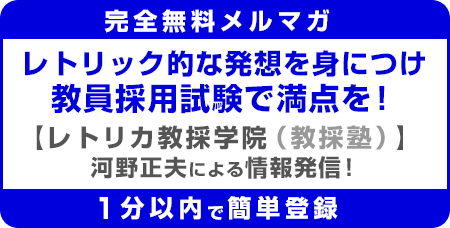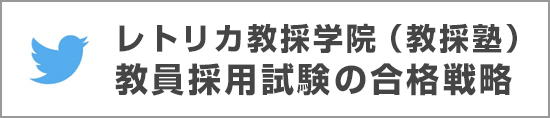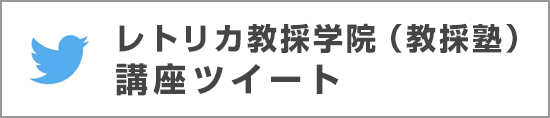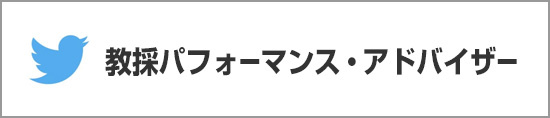【川上貴裕】ICT軽視の罠。これだから、いつまで経っても、日本の教育は、発展できないのでしょうね!
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: 教育論
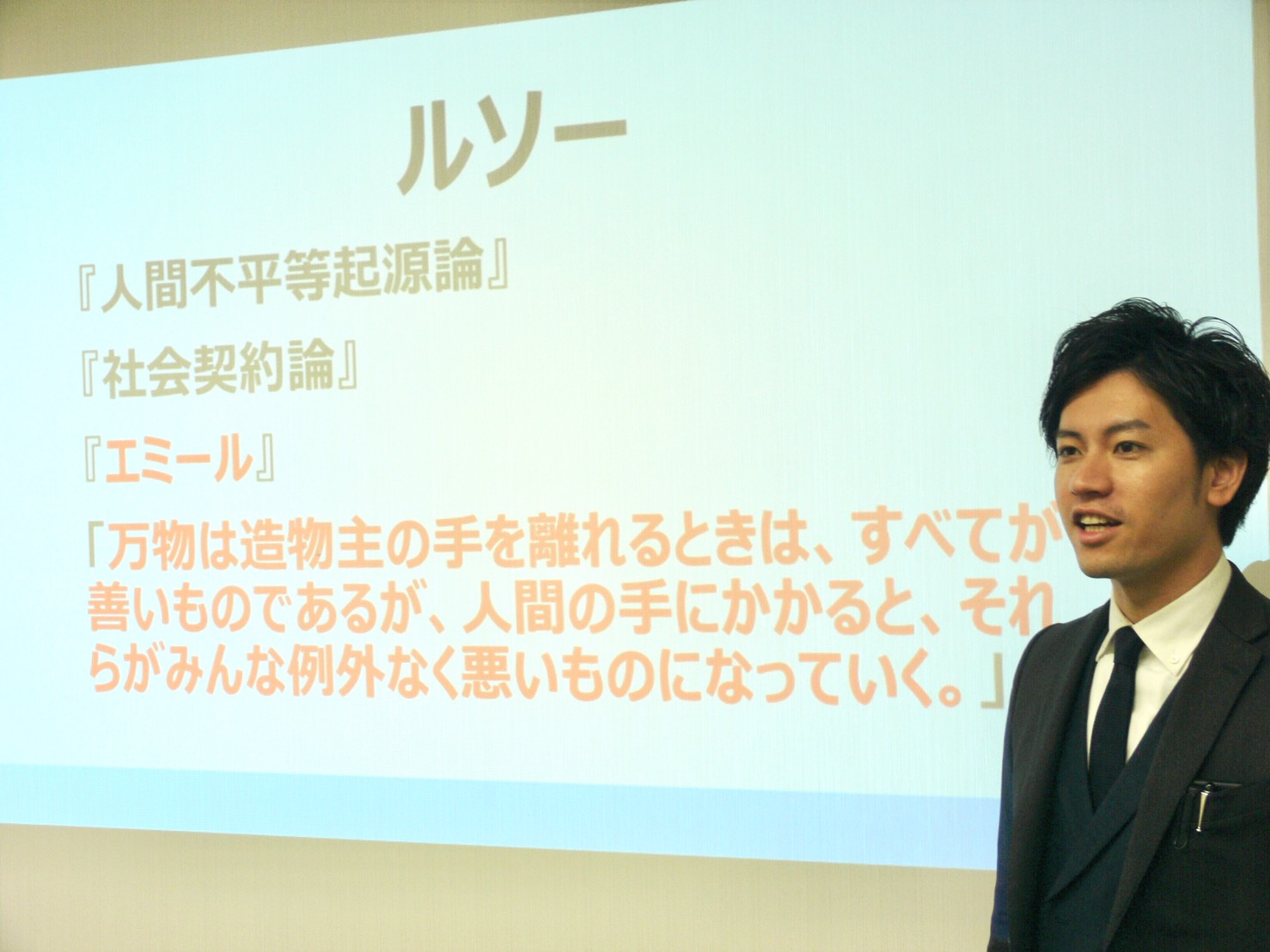
【レトリカ教採学院】ブログDE教採
【レトリカ・ブログ】
教採塾の川上です。
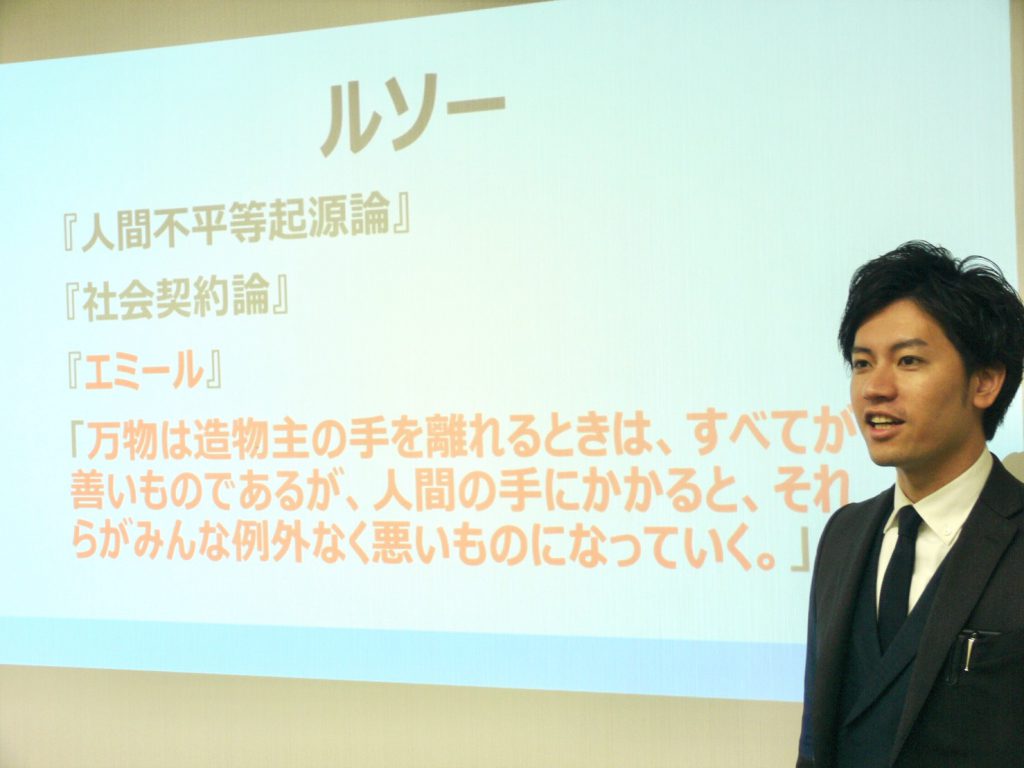
12月初旬、学習到達度調査(PISA)で、日本の生徒の読解力が、大きく低下したことが、報じられましたね。
そもそも、PISAで測定される読解力とは、
①情報を探し出す
-テキスト中の情報にアクセスし、取り出す。
-関連するテキストを探索し、選び出す。
②理解する
-字句の意味を理解する。
-統合し、推論を創出する。
③評価し、熟考する
-質と信ぴょう性を評価する。
-内容と形式について熟考する。
-矛盾を見つけて対処する。
これらを指します。
(国立教育政策研究所より。)
ただ、最近、ひしと感じるのは、これらの、測定される『読解力』のうち、『③評価し、熟考する。』という項目については、生徒の低下だけに、留まらない気がしています。
これらを報じている記者、記事を読んでいる教師などの、社会人も、既に、著しく低下しています。
特に、先ほどの③の項目のうち、『質と信ぴょう性を評価する』、『内容と形式について熟考する』という部分の、いわゆる、『情報分析能力』の低下は、大々的に報じるほど、今に始まったことではありません。
というのも、読解力の低下と聞いて、昔の古い価値観のまま、アップデートされていない人は、「読書量が減ったからだ。SNSを使い続けているからだ。」というような方向性を、自分で分析することもなく、鵜呑みにして、一方的に語ります。
もちろん、一部、その視点も重要でかつ、事実だとは思います。
しかし、読解力低下の本質は、もっと別の部分にあります。
その本質の分析なくして、ただ、「読書量が減ったからだ。最近の若いもんは・・・」ということでは、それを語る人自身の、読解力・分析能力の低さを、自ら露呈しているに過ぎません。
実に、恥ずかしい・愚かしい限りですよね。
読解力低下の本質の1つとして、PISAの学力調査が、Paper Based Testing(PBT=紙ベースによるテスト)から、Computer Based Testing(CBT=コンピューターベースによるテスト)になったことが、挙げられます。
2018年のPISA(2019年12月に調査結果発表のもの)では、245問のうち、7割にあたる173問が、CBTの形式で行われました。
操作方法も、
★長文の課題文をスクロールして読む。
★ローマ字入力で解答入力する。
★複数の画面で課題文を提示(Webリンクのクリックやタブの切替えで他画面に移動)
★マウスによる解答選択
★ドラッグ&ドロップ操作で画面上の選択肢を動かして解答
というように、生徒にとっては、かなり複雑な作業を強いられました。
これらの状況から、
日本の生徒にとっては、あまり馴染みのない、多様な形式のデジタルテキストや文化的背景、語彙・概念などが使用された問題が増加し、かつ、現在の日本の学校教育が芳しくないがゆえに、今回の読解力低下が引き起こされたと言っても、過言ではありません。
具体的に、説明しましょう!
日本の学校教育は、未だ、紙で書くことが、一番良しとされています。
そのような思考のまま、現在まできています。
加えて、普段、教科書やテスト、資料などで、文章を読むにしても、学校で教わった、『重要なところは線を引く』という癖がついています。
だからこそ、パソコン上で、線を引くことができないテストにぶつかると、その今までの慣れのせいで、応用できないのです。
単純な話、仮に、日本の学校で使用されている教科書が、全て個人のタブレットで閲覧できるようになるだけでも、CBTに対応できる子供は、どんどん増えていきますよ。
ここまで言うと、むしろ、読解力低下の原因は、学校教育への予算が無さすぎること、というのが、挙げられそうな気もしますけどね(笑)
もっというと、上記のことを述べると、今度は、「子供たちの目が悪くなる!」と言い出す連中も出てきそうですが(涙)
これだから、いつまで経っても、日本の教育は、発展できないのでしょうね。
さて。
一方で、読書量不足に伴う思考力の低下が原因だと、報じている記者や、そう考えている教師もいることでしょう。
先ほど述べたように、もちろん、その原因もあることにはあります。
しかし。
では、単に読書量を増やせば、読解力は、増加するのでしょうか。
件(くだん)の、CBTのそれと同じように、根源の分析もしないまま、「読書量を増やせ!」というだけでは、教師は務まりません。
脳科学と幼児教育の専門家である、杉田昌穂氏は、「読書量が増えても、文字情報を音声情報に変換するのが下手な人は、結局、思考が上手くいかず、読解力向上には繋がらない。」と、述べています。
目で見た文字による情報は、そのままでは、脳の記憶装置には入りません。
目で見た文字は、音声情報に書き換えられた後、脳の記憶装置に記憶されます。
だから、注意深く文章を読む時は、自分の頭の中で声を出して読み返したり、時には、ぶつぶつ小声を出しながら読むこととなります。
皆さんも、よくやっていることと思います。
従って、文字情報を音声情報に変換するのが下手な人は、変換作業に集中しているために、思考が上手くいかない(思考する余裕がない)のです。
こういう人達に、例えば、読書後の感想を聞くと、感想になっていないことが多いですよね。
文章の内容をコピーしたことを、そのまま述べるだけです。
小学校低学年によく見られる現象ですが、最近は、必ずしも、子供だけに限ったことでは無くなっているようにも思えます。
残念ながら、大人でも、そういう人を、よく見かけますよね。
(年内最後の私のブログにも関わらず、皮肉ばかりでしたね(笑)申し訳ございません!)
音声情報への変換の手立て、支援方法は、また別に考えるとして。
つまり!
思考が上手くいかない人もいるので、単に読書量を増やすだけでは、読解力向上に、直接的には、繋がらないのです。
ここまでの分析をした上で、読書量どうこう言うのであればまだしも、多くの人は、「読書量を増やせば、読解力向上に繋がる!」、そう、単純に、根拠もなく、せいぜい自分の経験や価値観だけで、考えているのではないでしょうか。
教師がこれでは、いけませんよね。
情報分析能力の基礎である、『質と信ぴょう性を評価する』、『内容と形式について熟考する』を、今一度、その人自身に、身に付け直していっていただきたいものです!
最後に。
27日より、年末年始休暇に入るため、本日で、2019年、最後のブログとなりました。
これまで、私の稚拙な文章に、お付き合いいただきました、読者の皆さん、誠にありがとうございました。
時には、数千viewとの表記があって、それだけ、自分の思考を、記載する責任に、ドギマギしたものです。
2020年は、
より、皆さんに共感していただける、ためになる、パワーアップしたブログを、お届けできればと思います!
また、11月期より、教採塾の講座を、ご受講いただいている皆さん。
あっと言う間の2か月が過ぎましたが、いかがだったでしょうか?
各講座でもお話している通り、今年の受講生の皆さんは、特に、素敵な方、多様な価値観と、鋭い感性をお持ちの方、愉快な方が多く、主催者側である河野・Ryo・川上も、毎回の講座に行くことが、楽しみでなりません。
先日の東京校でも、20名もの受講生の皆さんと、忘年会を開催することができ、大変、ありがたい限りでした!
(最後の記念撮影の写真をご希望の参加者は、教採塾公式LINE http://nav.cx/7NVbTEN より、ご連絡くださいね!)
自主的なご参加による、この人数は、教採塾の忘年会史上、初のことです!(笑)
そのくらい、和気あいあいと、仲良く、楽しく講座ができる環境・仲間に、我々も感謝しております。
1月の講座で、各校舎の皆様に、またお会いできますことを、心待ちにしております!
では、皆さま、よいお年をお迎えください!
2020年も、何卒、よろしくお願い申し上げます!
川上貴裕