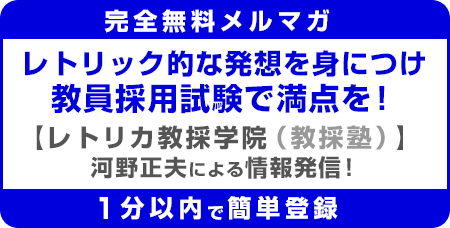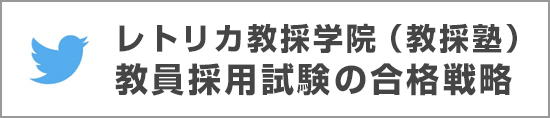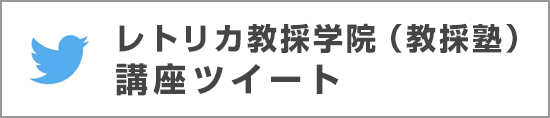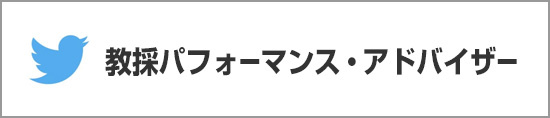料理から,科学的・構造的な思考を学び,授業に活用することもできますよ!
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: 教育論

【教員採用試験のバイブル】
教採塾の川上です。

私は、料理が好きで、基本的には毎日自炊をしています。
包丁も16本以上常備しており、食材や場面に応じて、使い分けています。(河野からは、「武器庫」と呼ばれています(笑))
受講生や河野からの要望があれば、ワインに合う料理を作ってパーティもしています。
本日のブログは、料理自慢をするわけではありません。
料理は、実は、子供を惹きつける授業を組み立てる上で大いに役立つ、ということを知っていただきたいのです。
料理において、有名な先人の言葉として、「さしすせそ」がありますよね。
「さ」・・・砂糖
「し」・・・塩
「す」・・・酢
「せ」・・・醤油(旧仮名遣いで「せうゆ」と記載。)
「そ」・・・味噌
私は、これらの調味料を科学的に分析しながら、料理を作っています。
(と言っても、匙加減は目分量と味見をしながら決めているだけですが。)
砂糖は、分子量が大きいので、できるだけ先に入れます。
仮に塩を先にふり、後で砂糖をいれると、分子量の違いから、なかなか染み込みません。
酢は、先に入れる(漬けておく)と食材は柔らかくなりますが、蒸発するので、酸味はさほどないですが、後に入れると、酸味が強く残った料理になります。
醤油は、最後に入れて味を調えます。先に入れると煮詰まったり、酒や野菜の水分で、味が薄まり、更に追加しないといけなくなり、味が整いません。
味噌は、風味を残す為、最後に入れます。肉や魚の臭みを取って旨味を倍増させる味噌煮などは、最初に入れます。
と、「さしすせそ」の1つをとっても、何を作るか、どう作るかによって、臨機応変に手早く料理を作らなければなりません。
調味料の手順に慣れてくると、今度は、
見た目の美しさ、バランス。
食材をどう切ったら味が染み込みやすいか。
どう調理すれば、栄養価が流れ出ないか、煮崩れしないか。
燻製の場合は、食材の水分含有量に合わせ、どう火加減を調節すれば、風味豊かな燻製にできるか。
(水分含有量と火加減を読み違えると、酸っぱいだけの燻製になってしまうので。)
といったことを、手を動かしながら、頭を回転させながら、常に同時進行でやっていきます。
料理は、手間をかけた分だけ、おいしくなります。
そのためには、上記のようなことも考えながら作らなければいけませんが(笑)。
しかし、上記のようなことが自然とできるようになると、構造的な思考がぐんと伸びます。
逆算的な思考も身に付きます。
授業も同じで、科学的な分析をもとに、構造的な思考をもって授業を組み立てると、面白いほど、授業に深みが増します。
授業のまとめ・落としどころから逆算して導入や発問を考えると、子供たちもぐっと食いついてきます。
「ここで、こんな発問を投げかければ、子供たちはしっかりと考えられる。」
「授業の要点に気付かせるためには、○○と対比させた導入をすればいい。」
「子供が結論を導き出すためには、この考察に落とせばいい。その考察に落とすためには、展開で・・・」
というようなことが、みるみる頭に湧いて出てきます。
ここまでいくと、いわゆる「ゾーンに入る。」という感じです。
本当に、子供たちも毎回の授業を心待ちにしますし、授業を組み立てる教師自身も楽しく準備することができます。
皆さんもぜひ、料理から科学的・構造的な思考力や分析力、認知力などを磨いてみてくださいね!
教採塾
川上貴裕