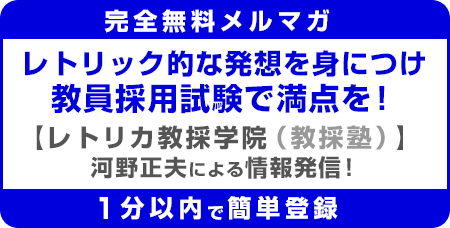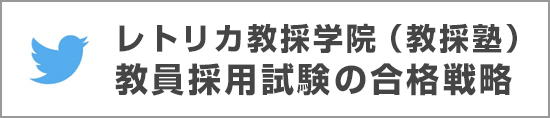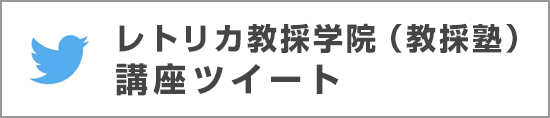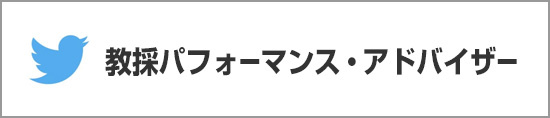感性(センス)・発想力を高める。
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: 教育論

こんばんは!
教採塾の川上です。

前回のブログに引き続き、本日は、ちょっとしたことから始められる、感性や発想力を高めるための方法をご紹介します。
まずは、感性の部門から。
①離見の見(りけんのけん)の視点を身に付ける。
世阿弥の『花鏡』に出てくる言葉です。
離見の見とは、演じている自分の姿を第三者的な視点で見ること。つまり、客観性を意味する言葉です。
現在の言葉で言うなれば、メタ認知(自分の思考や行動そのものを対象として客観的に把握し認識すること。)とも言えます。
ただ、ひとえに「客観性を身に付けろ。」と言われても、難しいものです。
一番、効果的に身に付けることができるのは、
他者を使って養っていく方法です。
テニスの「インナーゲーム理論」に基づく指導法では、サーブがオーバーしてしまう人には、自分がどのくらいアウトしたのかを言わせる方法をとっているそうです。
例えば、本人が「50センチ(アウトした)」と申告したら、コーチが即座に「1メートル」と実際の数字を言います。
正確な情報を伝えることで、感覚の修正を図ります。
このように、コーチという他者を使って、客観性を身に付ける練習方法です。(齋藤孝・著の「型破りの発想力」より。)
私がスターバックスに勤務していた頃は、コーヒーマスターとして、新人パートナーの指導もおこなう中で、「察すること」を何よりも重要視していました。
新人の子は、目の前の業務が手一杯となり、視野が狭くなりがちです。
例えば、
・ベビーカーを押しているお客さんが席を立ったら、新人の子に教えてあげて、状況を把握させた上で、どうしたらいいかを考えてもらう。瞬時に、「扉を開けてあげるとスムーズ。」という回答が返ってきたら、実際に行ってもらう。
・荷物をまとめだしたお客さんがいらっしゃったら、立ち上がった瞬間にコップや紙くずなどを回収することで、スムーズにお帰りいただけるようにする。
・あるとき、上着を羽織ったお客さんがいらっしゃったら、これまた先ほどの流れに従って、やり取りをした後で、室内の温度を調整してもらう。
・席を探しているお客さんがいらっしゃったら、代わりに席を探してあげて、空いていたら、そちらへ促す。空いていない場合は、きちんと状況をお客さんに説明して、最善の方法に導く。
・コーヒー豆の陳列棚を見ているお客さんがいたら、ただ声を掛けるのではなく(声かけられるのが嫌いなお客さんもいらっしゃるので)、その見ているコーヒーを実際に淹れて、「よかったらどうぞ。」と試飲してもらう。
気になる方は、さらに、そのコーヒーについて質問が来るだろうし、見ているだけの人であれば、そのあとは、下手に話し続けるのではなく、自由に見てもらう。
・あるとき、「お客さんの表情見た?一瞬、お客さんの表情が曇ったことに気が付いた?」と新人の子に尋ねてみる。
など。
このように、気付いていない新人には、気付かせてあげることはするものの、お客さんの視点で常に動くことがなぜ重要なのか、なぜその行為が必要なのかは、本人に考えさせます。
誰でも、慣れてくれば、自然と視野は広がるものですが、新人の子にとっては、なかなか難しいものです。
ここでも、新人の子は、川上という他人を使っていくことで、視野を広げ、自分を客観視するための物差しを形成していきます。
教育の世界で言うのであれば、公開授業もそうです。
実際には、完璧に作り上げた授業だったとしても、見ている側からすれば、違って見えていたり、自分では、大きな声で授業を進めていたと思っていても、実際には、小さかったという反応が返ってきたりします。
このように、他人の指摘によって、主観と客観の誤差を縮めていくことが効果的です。
(余談:客観性を身に付ける上でも、また、授業改善の上でも、公開授業はとても効果的ですが、準備に膨大な時間を要するため、あるいは、指摘されるのが怖かったり、自信を失うのが怖かったりで、なかなかやりたいという人はいませんよね(笑))
②一流を知る。
何事も、基準が無ければ、比較することができません。
一流を知ることで、明確な基準・物差しができ、物事の良し悪しがはっきりと分かるようになります。
二流、三流だけしか知らなければ、二流、三流であっても、それが一流だと勘違いすることもあります。
世の中には、多くの情報、モノ、考えなどが溢れています。
その中から、一つのもの・正しいものを選ぶ上で、一流を知っていれば、何を基準に選択すればよいかという視点が定まるのです。
一流を知ることで、自ずと感性は磨かれていきます。
③芸術鑑賞
「なんだ、拍子抜け!!」と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、ありきたりこそ、一番の近道だと考えています。
美術館に行って、絵を見るのもいいのですが、その美術館の空間自体が、感性にあふれたものですので、私もしばしば、美術館に行っては、ぼーっとしています(笑)
一流の方の書籍を読んだり、感性が近しい人、不思議な感性を持っていらっしゃる方の書籍を読むのもいいと思います。
「唾液も口の中では、体の重要な要素という存在だけど、口の外に出した瞬間、それは汚いものとして認識される。この感覚がずっと不思議だった。なぜそうなんだろうと。」と、芥川賞受賞小説家の川上未映子さんが仰っているのを拝見して、「近しい感性の人がいた!」と一方的に決めつけて(笑)、それ以来、川上未映子さんの書籍をすべて読んでいます。
こういった、私たちの周りでは当たり前の感覚となっているものを再認識することも、感性を磨く上では重要です。
川上未映子さんの作品、特にエッセイや対談ものなどは、本当に独特の世界観で、感性も豊かです。
かつ、説得力もあり納得するもの、驚きと発見のあるものばかりです。
教育の感性を磨くのであれば、教育界のカリスマ、有田和正先生の書籍「人を育てる」「教え上手」がおススメです。
私は、いわゆる、「褒めるシャワー」的なものが苦手ですが、有田和正先生の書籍では、ありきたりではなく、どのような褒め方がいいのか、どうやったら子供が主体的に成長するのか、逃げ場のあるしかり方とは何ぞや、追及の鬼の育て方とは何ぞや、など、「そうそう!そういう教育をしてほしい。」、「自分もそういう先生であれたらな。」、「こんな先生が増えるといいな。」と思えるものばかりでした。
映画で感性を磨く、というのであれば、
これは私の方法なのですが、同じ作品でも、3回は観るようにしています。
1回目は、英語音声・日本語字幕。
2回目は、吹替・英語字幕。
3回目は、英語音声・字幕なし。(吹替・字幕なしでも可)
で観ています。
1回目は、普通に観るのですが、
2回目は、日本語のセリフを聞きながら、英語の字幕を読むことで、「このニュアンスは英語ではこのような表現を使っているのか!」というように、英語の感性・言葉の感性を磨くことができます。(日本語音声でも、言い回しや字数の制限により、正確でない部分もありますが。)
3回目になると、セリフも覚えてくるので、字幕を取り除き、今度は、表情に注目します。
「このセリフの時には、こんな表情で話せば、相手にこのような印象を与えることができるのか。」という感じで、今度は表情がもつ性質・印象を研究し、感性を磨いていきます。
また、私は映画を観る上で、俳優と監督で作品を選んではいますが、
エマニュエル・ルベツキ監撮影督の、ミリ単位で調整されている映像美・息をのむほどのロングテイク。
クリストファー・ノーラン監督の、忠実な理論に基づいた世界観・迫力・可視化。
宮崎駿監督の、繊細な色彩・物語の訴求力。
彼らの作品は、圧倒的な感性があふれているものばかりなので、お時間がある方はぜひ。
もちろん、漫画から感性を養う、というのもいいかもしれません。
「人生の大切なことは、すべて漫画から教わった!」というようなコミュニティも数多く存在しますので(笑)
さて、続いて、発想力を高めるちょっとした方法のご紹介です。
④マインドマップを作る。
用紙のど真ん中にキーワードを書き入れ、そこから樹形図やマインドマップのように、中央のキーワードから連想される言葉を周りに書いていきます。
最初は、簡単な連想で構いません。
海→夏→スイカ・・・
慣れてくれば、今度は、少し難易度を高くしつつ、瞬時に連想できるようにします。
海→外国→夜景・・・
教育に関してであれば、
教育に関するキーワードを真ん中に置き、そこから連想していきます。
主体的な学び→子供たちに驚きと発見→導入で→意欲・関心が高まる・・・
これらのキーワードをまとめていけば、面接などで聞かれても、自分の核となる想い、教育論が語れるようになります。(内容の筋が通っている・整合性がある、という前提ですが・・・)
語りにおいて重要なのは、発想です。
発想=あるテーマをどんな視点・切り口で話すか、ということです。
発想や、語りの視点・切り口を磨く上でも、先ほどマインドマップのトレーニングが役に立ちます。
以上、感性や発想力を磨く、ちょっとした方法のご紹介でした。
ただ、前回のブログでもお伝えし、書籍「センスは知識からはじまる。」 水野学・著にもあるように、感性や発想力の基盤となるものは、なんといっても知識や教養です。
知識や教養が無ければ、ものすごく有名な絵画を見ていても、何の感動も湧きません。
映画を観ても、ストーリーが理解できなかったり、隠喩表現にも気付くことができなかったりします。
教師を目指すにあたり、教師(志望者)自身が、常に学び続けて、幅広い知識と教養を身に付けることが重要です!!!
では、また7の付く日に!!
川上貴裕