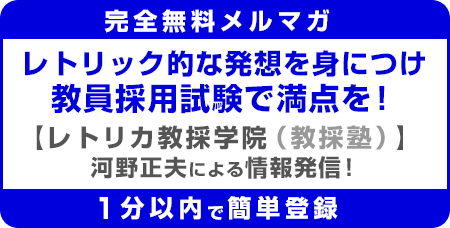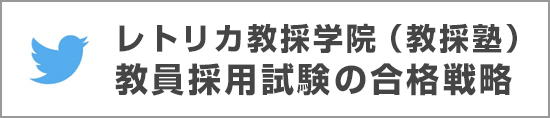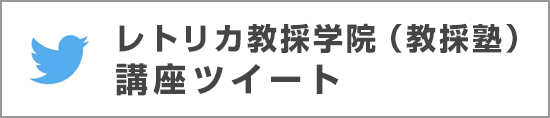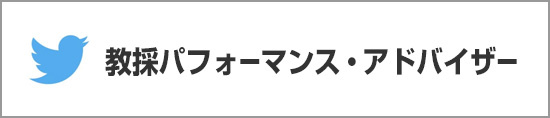しだいに好きじゃなくなっていくような学びを変えていきましょう!
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: 教育論

昨日、日本大学の宮川選手が記者会見をしました。
私も生中継で見ていました。
宮川選手は、会見の中で、
アメフトは大好きだったけれど、大学に入ってから、だんだんと好きではなくなった。
という趣旨のことを言っていました。
この言葉を聞いて、私は深く考えさせられました。
今日のこのブログ記事では、私は、いわゆるこの事件について論ずるつもりはありません。
私が注目したいのは、宮川選手の上記の言葉で表現されていることの中に、日本の教育が抱えるある問題が浮き彫りにされているということです。
私たちは、小学校に入学した当初は、勉強が好きで好きでたまりませんでした。
なんでも学びたいと思っていました。
授業中も積極的に手を挙げて、発言しました。
次の時間は何を学ぶのだろうと、ワクワクしていました。
時には、授業がよく分からず、宿題ができずに、泣きべそをかくこともありました。
でも、先生にやさしく教えてもらったり、友達に教えてもらったりして、分かるようになり、できるようになると、嬉しくて、もっと勉強しよう!と感じました。

↑
(この画像を、教採塾のアイコンに使っているのも、実は、そうした小学生時代には誰にもあった学びの喜びを表現するためです。)
それが中学校に入り、高校に進学すると、いつしか、勉強が嫌いになってきます。
すべての教科が嫌いになるとは言いません。
でも、勉強に、やらされている感、やらなくてはいけない感、できればしたくない感が出てきます。
教室でも、積極的に手を上げたり、発言をしなくなります。
先生がお休みで、授業が自習になると、大喜びします。
高校を卒業して、大学受験に合格し、大学に入ったら遊びまくるぞ!と決意します。
最高学府である大学に進学するのに、「さあ、遊ぶぞ!」と強い決意を胸に秘めます。
すべての人がそうだとは言いません。
いつもそうなるとは言いません。
でも、多くの人が、感じているのは確かでしょう。
何が原因なのでしょうか?
成長に伴い、思春期となり、小学生とは違う感性を身に付けるから。
高校受験、大学受験があり、勉強が受験マインドになるから。
受験勉強が暗記中心で、面白くなくなるから。
どれも、それなりに正しい解答でしょう。
でも、私は、あえて、指導者(教師)がつくる雰囲気が大きな原因だと考えています。
小学校の先生は、学びに喜びを与えてくれます。
小学校の先生は、できたことを心から褒めてくれます。
小学校の先生は、子供の存在を喜び、認めてくれます。
でも、中学校に入学すると、高校入試のための受験勉強に主眼が置かれるようになります。
高校に進学すると、大学入試のための受験勉強が大きなウエイトを占めるようになります。
中学校や高校のすべての先生が、受験勉強ばかりさせているというつもりは全くありません。
素晴らしい教育を実践されている先生方もたくさんいらっしゃいます。
でも、なぜか、中学校は高校受験のため、高校(特に普通高校)は大学受験のため、という雰囲気があります。
いつの間にか、生徒も教師も、その雰囲気に呑み込まれてしまいます。
そして、勉強が苦行になります。
学びの喜びが内発的動機にならず、受験に合格するという外発的動機のみで、勉強をすることになります。
そこには、ワクワク感も、好奇心も、学びの充実感もありません。
暗記することを中心とする勉強が始まります。
暗記は暗記でも、小学校2年生が「九九」を覚えるときのような、楽しさも、ゲーム感覚もありません。
小2で覚えた「九九」は、私たちは死ぬまで忘れませんし、毎日、必ずどこかで使っています。
中学校や高校で暗記したことの多くは、受験が終わると、忘れ去られます。
大学受験の前の高校生は、大学入試に合格したら、覚えたことは全部忘れてもいいとすら思っています。
将来、役立つこともなく、入試後はほぼ確実に忘れることがわかっている勉強を毎日続けるわけです。
苦行になるのは当然です。
中学校や高校で、もし、教師が、授業をはじめとするあらゆる指導で、生徒に、好奇心と興味と関心と学ぶことの喜びを感じさせ続けたら、勉強は苦行にならないでしょう。
そういう実践を展開していらっしゃる中高の先生方もいらっしゃることは事実です。
ただ、そういう先生方が圧倒的な大多数ではないことも事実のようです。
このブログ記事の冒頭で触れた宮川選手も、きっと大学に入る前は、アメフトを楽しんでいたのでしょう。プレイするのが楽しく、自分の腕が上がっていくのが嬉しかったのでしょう。大好きだという言葉がそれを表しています。
でも、きっと宮川選手は、日大に入って、ただ勝つためだけ、どんなことをしてでも勝つためといった雰囲気が嫌になったのかもしれません。
アメフトは競技ですから、勝つことが目的なのは当然です。
でも、プレイする喜び、勝つことによる充実感・達成感を一切感じさせないような雰囲気が存在すれば、プレイすることも、勝つことも喜びにはつながらなかったのでしょう。
大好きなものが、好きでなくなる過程が手に取るようにわかります。
私は、アメフトについて何も知りませんから、アメフトについては語れません。
でも、教育については、私の人生で、ずっと考えてきました。
やはり、指導者(教師)が創り出す雰囲気が、学ぶものに大きな影響を与えます。
学びの主役は学習者ですが、学びの環境を整える最終責任者は教師です。
学びの環境を整えることができない指導者は、指導者失格です。
学びの環境によって、学習は苦行にもなり、喜びにもなります。
学びを喜びに感じさせる教師になりたいものです。
私は教採塾という、教員採用試験対策講座を主催して、16年になります。
教採塾は、教採という受験のための講座を開講しています。
でも、私は、いわゆる昭和型の受験勉強を受講生に強いたことはありません。
教採塾での学びは、筆記試験対策講座であれ、2次試験(面接)対策講座であれ、学ぶ喜びに満ちたものであり、教採という受験が終わった後も、確実に使える知識と技術と哲学を指導しているつもりです。
多くの元受講生たちが、教採塾で学んだことの多くを、教採合格後の日々の学校現場で活用していると言ってくれています。
とても嬉しい知らせです。
また、私が指導した面接の極意や戦略を、中学校や高校で、生徒たちに伝えてくれているのだそうです。
これも嬉しいことです。
こうして、私が講座で語ったことが、次世代の若者たちの間に広まっていると聞くだけで、教採塾を始めてよかったと感じます。
私の指導が厳しいという噂があるそうです。
私が指導に関して、冷静で、科学的で、評価が客観的であることは事実です。
しかし、私は、昭和型の怒鳴ったり、恫喝したり、侮蔑するような指導はしません。
私は、よく自分のことを、エンジェルだと言います。
受講生なら、私がエンジェルだということを理解してくれると思います。
私の講座には、笑いが絶えません。
楽しいからです。
面白いからです。
受験対策講座ですから、教採合格も勝ち取れますし、合格の後も、教採塾で学んだことは、一生、使えます。
私は、教採が終わったら、すぐに全部忘れてしまうような指導をしたくありません。
いつまでも役に立ち、次の世代の子どもたちにも伝えることができるような指導をしていきたいと思っています。
だから、教採塾は、「予備校」と言われることを潔しとしません。
受験のための講座であり、合格のための講座ですが、合格を勝ち取りながらも、一生、使える知識と教養、語りの力を身に付けて欲しいと願っています。
だからこそ、私はエンジェルですが、学びそのものには妥協をしません。
ダメな学びにはそれではダメだと申し上げます。
常に冷静に申し上げます。
でも、冷静な評価を受け入れることができない人が、時々、退塾します。
致し方ないことです。
自分を客観的に評価され、伸ばしてもらうことから逃避し、何も言われず、ただ、受け身で講座に座っているだけでいいという人は、教採塾には向いていませんから、退塾を引き留めたことはありません。
教採塾は、どんな人に対しても、苦行を強制することはありません。
私自身の話が長くなってしまいました。
話を戻しましょう。
大好きだったことが、しだいに好きではなくなるというのは、悲劇です。
本当に悲しいことです。
小学生も、中学生も、高校生も、そして、おそらく大学生も、入学の日には、何らかの期待感とワクワク感があるはずです。
小学生はその期待感とワクワク感が何年かは続きます。
中学・高校・大学は、入学以降、何日単位で、その期待感とワクワク感が消失していきます。
期待感とワクワク感が消え去らないようにするのが、教師の最大の仕事だと私は考えています。
教採塾から、教採に合格し、学校現場に立っている多くの先生方は、その期待感とワクワク感を持たせ続けようと、日々、奮闘していらっしゃいます。
時々、フェイスブックやツイッターなどで、そういった実践の話を拝読し、心から喜んでいます。
教採塾の直接的な役目は、教採合格で終了します。
しかし、教採塾の夢と理想は、教採合格後を見据えています。
だから、教採塾の講座は、好奇心が持てて、楽しく、笑いが絶えず、期待感とワクワク感が持続するように、日々、工夫しています。
元受講生の学校現場の先生方に負けてはいられません。
教採塾で学んでいる皆さん、現在、学校現場で日々、奮闘している先生方、
私からのメッセージがあります。
しだいに好きじゃなくなっていくような学びを変えていきましょう!
大好きが持続する学びをつくっていきましょう!
では、また明日!!
河野正夫