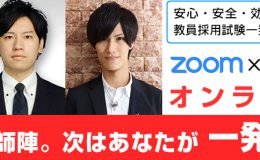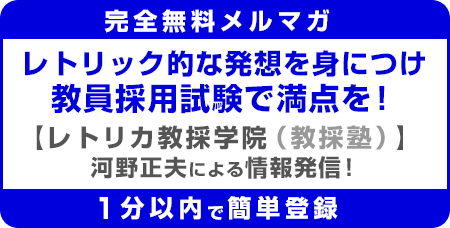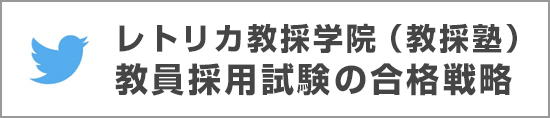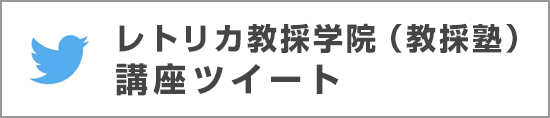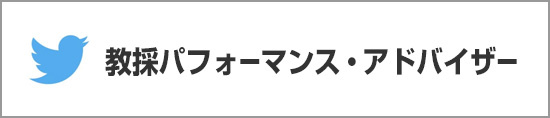主体的な学び,対話的な学び,深い学び,既に,たくさんやっていますよ!(微笑)
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: パフォーマンス力向上, 合格への戦略, 教育論, 筆記で満点を, 面接力向上
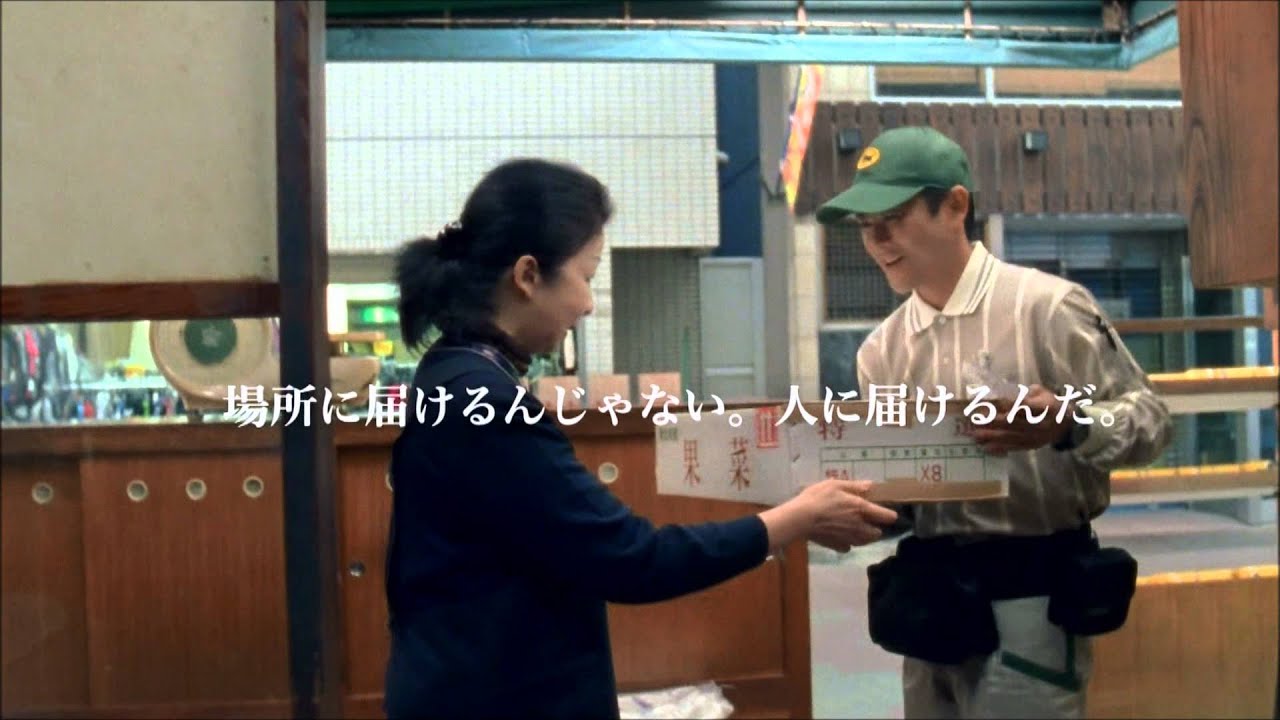
【レトリカ教採学院】ブログDE教採
【レトリカ・ブログ】
「主体的・対話的で深い学び」というフレーズが,新学習指導要領によって,教育界を席巻していますが(微笑),よく考えてみると,主体的な学び,対話的な学び,深い学びなんて,とっくに,たくさんやっているのではないでしょうか。
例えば,教採塾のオンライン講座の「面接満点講座」と「教職教養講座」は,まさに,主体的な学び,対話的な学び,そして,深い学びを,やりまくっていますよ!(微笑)
ちょうど,本日,12月第4週の課題の総評を,河野が投稿しましたので,その総評を,ここに転載してみますね。
面接満点講座
〔12月期・第4週総評〕
今回の3つの課題に共通していたのは,次のことです。
1.自己満足の語りではなく,聞き手(読み手)の心を予測し,相手の心を共感的に動かす語りが必要。
2.聞き手(読み手)に好感・共感を感じてもらうために,相手の心に刺さる言葉を選び,効果的に語ることが必要。
3.聞き手(読み手)には,一定の常識やマインドセットがあることを理解し,その常識やマインドセットを,よりインパクトある言葉で言い換えてあげることが必要。
講座資料にもありましたが,クロネコヤマトの,
「場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ。」
というキャッチコピーが大好評だったのも,こういうことです。

つまり,
顧客は,みんな,宅急便会社に,自分の荷物を大切に運んでほしいと願っています。
でも,その願いを,ただ単に,「私たちは,お客様の荷物を大切に運んでいます!」と言っても,顧客からは,「当たり前だ!お金払っているんだぞ!」と,かえって怒られますよね。
だから,そこを理解して,工夫を凝らし,
「場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ。」
としたのです。
確かに,宅急便は,荷物を,送り手の住所から,受取先の住所に届けます。
住所から別の住所へ,それは,いわゆる送り状に書かれています。
でも,実際は,送り手という人が,受取先という人に,荷物を送っています。
クロネコヤマトは,荷物を,ある住所から,別の住所に,トラックなどで運びますが,その荷物は,ある人から,ある人への贈り物であったり,届け物であったりします。
クロネコヤマトが繋いでいるのは,場所ではない。
クロネコヤマトが繋いでいるのは,人と人だというメッセージをこのキャッチコピーに込めたのです。
その時,顧客は,自分が無意識に感じていた,「荷物は大事に扱ってほしい。自分が心を込めて,あの人に贈る荷物なのだから。」ということを思い出します。
このキャッチコピーを見て,聞いて,これまで,無意識だったその自分の想いを思い出します。
そして,自分の想いが新たな言葉,「場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ。」で,満たされ,人は,このキャッチコピーに,大きな好感・共感を抱きます。
これが,キャッチコピーの仕組みであり,これが,人の心を動かす語りの仕組みです。
キャッチコピーは,短い言葉です。
それが,長くなれば,いわゆる語りやスピーチになりますが,それでも,原則は同じです。
人の心に無意識にある常識や想いを,新鮮な言葉で表現してあげるのです。
そうすれば,人の心は動きます。
人の心を動かすのは,実は,言葉ではありません。
人の心を動かすのは,人の想いです。
自分の想いに繋がる人の想いです。
思いの連鎖が人を動かす。
これが,語りの力の本質です。
教職教養講座
【12月期・第4週総評】
主体的に学習に取り組む態度をどのように評価するか。
親(保護者)による体罰禁止という法改正をどう考えるか。
障害のある子供への支援・配慮をどのように実践していくか。
簡単に言うと,この3つが,第4週の課題でした。
お一人お一人の回答には,河野が,個別にコメントをさせていただきました。
ここでは,総評として,もっと普遍的なことを申し上げますね。
態度の評価と言うのは,どうしても主観的になります。
主観的な評価自体が悪いわけではありませんが,主観的な評価には,価値観や美学が入り込みます。
つまりは,たとえ,達成度は低くても,習熟度は低くても,習得の量は少なくても,「一生懸命」に頑張っていたら,評価しようというものです。
でも,中には,既に,達成度・習熟度が高く,完全にわかっているから,特にその授業や課題にあまり意欲がない(つまりは,もうできているから,意欲はないが,完璧にできてはいる)という子供もいるでしょう。
その場合,その子供に意欲が見えないから,評価を低くすることが適切なのかという問題が出てきます。
もし,既にその課題の答えが完全にわかっていて,やや退屈している子供も,態度で高評価をもらいたいのであれば,「どうすればいいのかなあ?よおし,頑張って考えてみるぞ!」というお芝居をして,先生に見てもらえば,評価が高くなるということなのでしょうか?
実際には,このような問題・課題が,多くあります。
態度を評価するときの,評価基準の設定は,極めて,難しいものです。
その難しい評価基準について,考えていただきました。
具体的な総評は,川上に譲りましたので,ここでは繰り返しませんが,評価基準は,思いつきではダメです。
主観的な評価の評価基準であっても,評価基準そのものは,客観的に設定する必要があります。
皆さんも,この課題に回答するときに苦労されたものと思います。
親(保護者)による体罰禁止を定める法改正がなされました。
先進国の中では,最も遅く,遅きに失したと言えなくもないですが,まずは,この法改正がなされたことは肯定的に評価すべきでしょう。
これから,どうするか?
国民への周知は上手くいくのか?
学校は,教師は,どのように関わるのか?
そんなことを,この課題で,皆さんに考えていただきました。
日本は,まだまだ,子供は殴ってでも教育しなければいけないときがある!という人も多く(そう思う人が過半数という統計も多いようです),そう簡単には,周知徹底はうまくいかないかもしれません。
それを予測しながらも,なんとか,この法改正のスピリットを国全体に広めるために,学校教育が何をすべきなのか,あるいは,学校を離れて,地域レベル,そして,国レベルで何ができるのかを考えて見ることも大切ですね。
皆さんの回答は,そういうことに想いを馳せ,教師らしい,そして,人間らしい,素晴らしい回答が多かったですね。さすがです!
障害のある子供(発達障害を含む)への支援・配慮に関しては,皆さん,素晴らしい回答を投稿していらっしゃいました。
障害があるから支援するという考え方から,障害がある子供も,障害がない子供も,共にメリットがある,ユニバーサルデザインの支援を考えていくことが必要ですね。
ユニバーサルデザイン,口で言うのは簡単ですが(微笑),なかなか,そのデザインには工夫が必要です。
ユニバーサル・フォント,ユニバーサル・カラーなど,最近は,ヴィジュアルなものにも,ユニバーサルデザインの考え方が,適用されていますよね。
こういったことを踏まえながら,小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などで,どのようなユニバーサルデザインを考えていけばいいかということを考えるのは,有意義であり,また,ある意味で,楽しいことでもありますよね。
この講座は教職教養講座ですが,こうした課題を毎週3題ずつ考えて,回答していくことにより,皆さんの教職教養の筆記試験への準備だけでなく,面接・集団討論・小論文・グループワークなど,幅広い準備になっていることと信じます。
教員採用試験は,ある意味で,受験ですが,その背後には,やはり,教育学の学び,教育時事の学び,そして,人が人を育むという,教育の本質への学びが重要です。
単なる,筆記試験の受験テクニックだけでなく,それこそ,普遍的な学びができていること,受講生の皆さんが,その学びを楽しみながら,チャレンジしてくださっていることを嬉しく思います。
この調子で,これからも,どんどん学んでいきましょう!
と,こんな風に,こんな課題をそれぞれの講座で毎週3題ずつ,出題し,全ての受講生さんに,それぞれの課題への回答を,専用サイトに投稿していただいています。
受講生さんは,お互いの回答や,一つ一つの回答に対する河野のコメントをすべて読むことができます。
河野は,講座サイト内で,書籍を紹介したり,動画を紹介したり,有益な情報を発信しています。
もちろん,川上も,毎週総評を書いていますし,時には,個別のコメントもします。
オンライン校の講座は,まさに,主体的な学び,対話的な学び,深い学びを,実践しています!
オンライン校,本当に,盛り上がっていて,素晴らしいですよ!
では,また明日!!
河野正夫