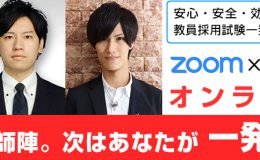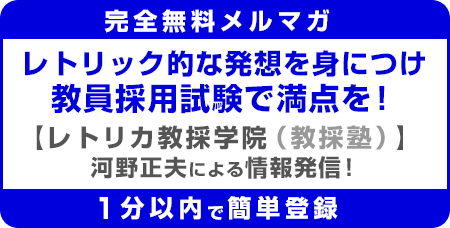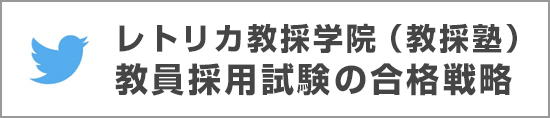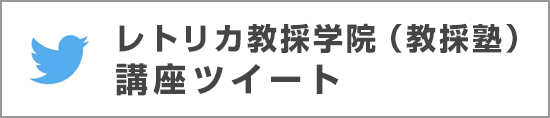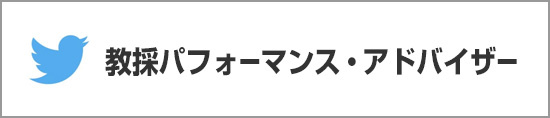時代に取り残された教員にならないように!
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: 合格への戦略, 教採塾の新企画, 教育論

教採塾の川上です。
10月からは,毎週,水曜日のブログ記事を担当します!

今日は刺激的な、挑発的な内容になるやもしれません。
教育界(高校・大学・教育現場など)や、受験産業化している塾・予備校にメスを入れていきます。
ちょっとだけタブーな領域に踏み込んだ話をしようと思います。
教採塾は、21世紀型の塾です。
【超】がつくほど、ICT企業です。
受講をお考えの方には、受講に関する情報の全てが記載してある、弊社のホームページをご覧いただければ、どんな塾なのかが一目瞭然となっています。
さらに,教採塾のブログ、ツイッター、フェイスブック、LINE@、様々な媒体で、日夜、情報発信をしています。
教採塾の息吹は,インターネット上の多くの場所で感じていただけるはずです。
しかし、お問い合わせの中には、ホームページの情報よりも、紙媒体(パンフレット・資料)を求めてくる方がいらっしゃいます。
手元に紙媒体があることで安心する、そんな昔からのマインドが離れないのだと思います。
(某省庁も、メールが流出した際、今後は紙媒体で金庫に保管する、という旨を述べていました。このように、いつまで経っても古い考えのまま、日本は進むのだと思います。)
過去に教採塾もパンフレットを作ってはいましたが、ホームページ以上の情報はそこには記載していません。
ホームページが、一番の情報源だからです。
ですから、今年から、紙媒体のパンフレットは廃止しました。
それでも、某予備校のホームページにも「資料請求」という欄があるように、それが当たり前だと思っている昭和型マインドが多い気がします。
ICTや情報教育というものを教育界全体で謳っておきながら、実際にその流れを取り入れると、「見にくい、不親切。」というレッテルを貼られてしまいます。
現場の話を聞くと、今の若い世代が、教室でタブレット端末を駆使した授業をしようものなら、「他のクラスと不平等だからやめて!」という先輩教員までいるのだそうです。
資料・紙媒体が欲しいのであれば、ホームページをスクリーンショットするなり、印刷するなり、いくらでも方法があると思います。
他のクラスと不平等ならば、アクティブラーニング・ICT化も謳われているので、学んで、タブレット端末が使いこなせるようになればよいだけです。
アクティブラーニングを推奨する教師・教師志望側が、一番アクティブラーニングができていないのではないかと感じています。
さて、次に。
教採塾には、入塾金というものは存在しません。
受講料も、月謝制で支払うだけの極めて簡単なものになっています。
しかし、教採塾Twitterの質問箱の中には、月々の受講料が高いのではないかというものがありました。
他の予備校・塾は、一括で入塾金と受講料を支払わないといけません。
もちろん、分割でも可能なようですが、審査を通したり、審査の際には、学生は親のサインや許可がないといけなかったり、と手続きが煩わしいですし、分割しても結構な値段になります。
また、教採塾は月謝制のため、途中退塾の場合は、1か月分の受講料をキャンセル料(退塾料)としていただくだけです。
他の予備校・塾では、一括で入塾金・受講料を払っているため、途中退塾をしても、満額残金が返ってこない場合もあるようです。
このようなことは、よくよくホームページや規約を読めば分かることですが、一括よりも、月謝制の方が高いと感じてしまう人が多いようです。
一括で30万弱の入塾金・受講料を払う方が、遥かに高いと感じてしまうのは私だけでしょうか。
それでも、「月2万円。」などと、月謝制の話をすると、高いと感じてしまうようです。
続いて。
教採塾には、本社はありますが、管理機能のみを担っており、受講生をお招きするような施設にはなっておりません。
しかし、お問い合わせの中には、「直接お会いして、講座についてお話を聞きたい。」という方が毎年必ずいらっしゃいます。
多分、これは説明会や資料請求が無いからだとは思いますが、先ほども述べたように、ネット上に全てが記載してありますので、不要なだけなのです。
各講師の想いや哲学は、講師が執筆するブログ記事やツイッター投稿などで、容易にご理解いただけるはずです。
「でも、直接お会いしてどんな人か確かめたい。」という方もいらっしゃいます。
しかし、某予備校・塾においても、説明会で直接講師が話す機会はほぼありません。
広報担当、事務担当が、講座の流れを説明するだけです。
講師が話すとしても、その講師が実際に、あなたの受講する講座の講師をするかどうかは分かりません。
上記のような質問を下さる方は、その人に会いたいのではなく、説明を聞いて安心したいだけなのだと感じます。
話を膨らませると、各都道府県の教採説明会、予備校・塾の説明会、何らかの説明会に参加しても、「有益な情報が手に入った!!」と思ったことはそう多くないのではないでしょうか。
「なんだ、ホームページに記載されていることだけじゃん。」と感じたことはありませんか。
教採の説明会の一部では、合格した教師の話を聞くコーナーもありますが、読み上げるものは、どれも主催者側が用意したのかというほど、ホームページや県や市が出す資料の言葉を並べたようなものだけで、「有益だ!」と思った試しありません。
続いて。
「自習コーナーがある。」を宣伝文句にしている、予備校・塾があります。
「自社ビルだから」「いつでも来られるから」と謳っていますが、そんなに自習コーナーっていいものなのでしょうか。
その宣伝文句を見て、「(特に大学受験の予備校で受講する高校生に多い。)無料で使える!」と思われている方もいらっしゃいますが、その自習コーナーの維持は、みなさんの入塾金・受講料から削られていることを知らないのかもしれません。
また、私個人としては、みんながぎゅうぎゅうに座っている中で自習をする方が、窮屈で気を遣わないといけない気がします。ちょっとした音が気になったり、出入りが気になったりして、逆に集中できなくなったりもします。
自習室で勉強する、というのは、勉強に参加している感・仲間意識の口実にすぎません。
勉強できる人は、放課後の教室なり、自宅なり、カフェなり、どこでも勉強はできます。(事実、カフェくらいの少しガヤガヤした空間の方が、集中力は高まるという研究報告もあります。)
グループの所属感に意識が行く人は、その意識だけで満足し、実際の試験や受験では、事実、あまりいい点数が取れていません。
加えて。
教採塾は、各講座24人がMaxの少数精鋭で開講しています。
だから、講座内でも、一人一人の質問に答えたり、アドバイスをしたりすることも可能です。
しかも、一貫して、通年で、河野、Ryoさん、川上がアドバイスをします。
かたや、大手の予備校・塾に行く人は、所属感を無意識のうちに満たそうとしているのかもしれませんが、大きな会場で、多くの受講生がいる中で、講師(毎回変わることもある。)の話を聞くだけで、果たして自分に合ったアドバイス、戦略を練ってもらえていますか。
他の人が合格した要因が、自分に当てはまるわけではありません。
他の人の学習方法が、自分にマッチするというわけではありません。
一般論を聞いても、それが自分で使えるかどうかも分かりません。
集団の仲間意識、参加している感に満たされているだけで、教採の合格は勝ち取れません。
自分には、自分にあった戦略や学習方法が絶対に必要です。
しかしそれは、大きな会場で、多くの受講生が講座を受けている中で見つけるのは、至難の業・不可能に近いです。
最後に。
教採塾はオンライン校・LINE@を、この度、立ち上げました。
電子メールでも、これまで概ね12時間以内に返信をしておりましたが、更に、質問しやすい、情報を提供しやすい、添削しやすい、遠くの方でもオンライン上で参加しやすいような環境を整備してきました。
しかも、その発信や回答、添削といったものは、必ず、河野か、私、川上がしております。
昭和型の企業・予備校・塾だと、添削や回答の設備は整っているものの、手段は郵送・FAXです。
絞った話をすると、
添削においては、往復の時間もかかる上に、添削相手が、毎回同じ人間とも限りません。
大手になればなるほど、送ってくる受講生は多いので、とてもではありませんが、同じ講師が添削することは不可能です。
となると、どうなるか。
実際は、院生や大学生をアルバイトとして雇い、彼らに添削をさせているところもあるようです。
(Twitter等SNSの発信についても、我々からすれば、毎回口調や内容や信念が違っているので、「これはアルバイト達に発信させているんだろうな。」というのがよく分かります。)
しかし、郵送する側は、見てもらっているという安心感で、そのようなところまで目はいきません。
ただ、真実を見ていくと、添削する者が変われば、一貫した指導は受けられません。
そのような、時間もかかり、添削も一貫性が無いものに、頼るべきなのかどうか、疑問に感じます。
以上、3,000字に渡り、タブーやからくりにメスを入れてきました。
教採塾が優れているんだ!という事が言いたいのではありません。
ただ、教師、教師志望者、予備校・塾などの中には、あまりにも古い、20世紀型の固定観念・既成概念に囚われ過ぎているところがあるような気がします。
アクティブラーナーであれ、ICTをもっと推進しよう、情報教育は取捨選択が大事だ!と謳っておきながら、自らが、そうなれていない人がいらっしゃるのが事実です。
教師自身がアクティブラーナーであれ!というのであれば、もちろん、教採の試験を受ける自分が、暗記という苦行で合格を勝ち取ろうとしていたのでは話になりません。
ICTを推進しよう!というのであれば、紙媒体依存や、直接人に会って確かめてからでないと、ということではいけません。
(SNSだって、見ず知らずの人や、遠く離れた世界中の人と交流ができる、それもメリットのはずです。ラインだって、顔や声を直接見聞きしているわけではありません。でも、普通に会話が成り立ちますよね。ラインでは問題ないことが、なぜか教育になると、どうして問題になるのでしょうかね。)
情報教育において、情報は取捨選択が大事だということを子供たちに教える教師として、しっかり調べもせず、分からないことは問い合わせればいいや、ではいけませんよね。
受験マインド、古い固定観念や既成概念は今日まで。
今年、教採を受験される方、予備校・塾に通おうとしている方は、上記を参考にしながら、しっかり見定めていってくださいね!
では、また来週の水曜日に!
川上貴裕