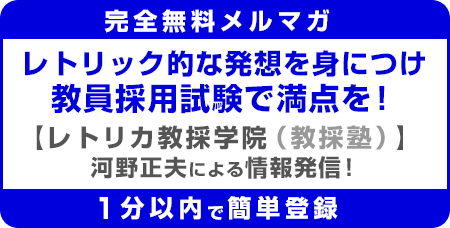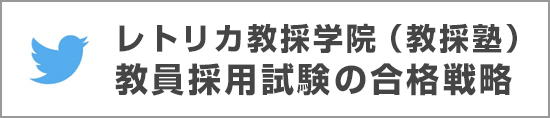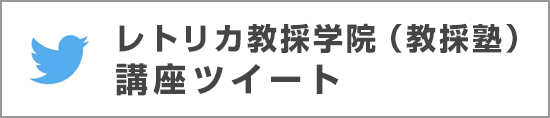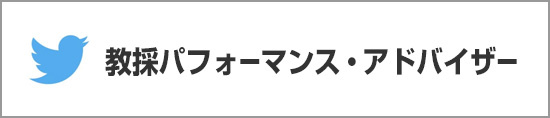面接において万能なアクティブ・ラーニングを駆使する。
- By: Kyousaijuku
- カテゴリー: 教育論

教採塾の川上です。

新学習指導要領に則り、「主体的・対話的で深い学び」が謳われていますよね。
「主体的・対話的で深い学び」は、「アクティブ・ラーニング」とも言い換えられます。
タイトルに「万能な」と記載していますが、今回のブログでは、アクティブ・ラーニングの良し悪しを議論するわけではありません。
「新出してしまったものは仕方ねえ!面接での自分の想いや核にでも使ってやろう!」というものです(笑)
持論ではありますが、アクティブ・ラーニングをしっかりと理解しておくと、おおよその面接での質問にも、軸をもって答えることができてしまうのです。
といっても、「アクティブ・ラーニングってイマイチ分からない!」とおっしゃる方もいますので、まずは、アクティブ・ラーニングをさらっと、川上なりに、噛み砕いて解説していきます。
この解説や、後述するサンプルなどを見ていただければ、「万能な」とネーミングした理由が分かっていただけることと思います。
そもそも「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」とは:
「主体的・対話的で深い学び」という言葉を聞くと、
「なんだなんだ!?新しい指導方法を導入しないといけないのか?」と思われがちですが、そのようなことはありません。
指導の方法云々というよりも、授業の工夫や改善を重ねること、というのがまず挙げられています。
ただ、「主体的な学び=子供たちの自主性を重んじた学習をすればいいんだ!」ということで、新しい指導方法を導入したり、授業改善をおこなったとしても、それは単に、学習を子供たちの自主性のみに委ね、学習成果に繋がらない、いわば「活動あって学びなし。」状態になりかねません。
更に言うなれば、「主体的・対話的で深い学び」は、毎時間の授業では実現できるものではありません。
単元や題材の中で設定していけばよいものとされています。(ただし、課題の解決や討論のみをやっていればOKということではない。)
授業の工夫・改善のポイントとしては、
既におこなわれている、言語活動(記録・要約・説明・論述・話し合い)や観察・実験などの質を高めながら、習得・活用・探究のサイクルを確立させること、とされています。
また、「主体的・対話的で深い学び」は、学習の基盤となる3つの資質を育成する、とされています
その資質とは、
① 言語能力
② 情報活用能力
③ 問題発見・解決能力
この3つです。
そうは言うものの、
個人的には、「言葉の意味は分かるけど、じゃあどういうこと?どうすればいいの?」と思ってしまいます。
私の理解能力が低いだけだとは思いますが、あえて言わせていただくのであれば、いかんせん、学習指導要領や答申の文言というものは、分かりにくいんですよね。
端的に述べると、学習の基盤となる資質とは、
頭の中の“引き出し”を増やすこと。
頭の中の引き出しが多ければ多いほど、視野も広がり、思考も深まり、いろいろな場面や用途に応じて、その引き出しから知識や知恵を出して活用し、課題を解決することができる。
ということではないかと考えます。
学習指導要領と答申よりも、漠然とした抽象的な表現になりすぎましたかね(笑)
では、ここからは、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」のそれぞれの視点で、子供たちにどのように学ばせるかを具体的に表現していきます!
子供たちを主体的に学ばせるためには:
① 分かる授業をおこなう。分かる授業とは、子供が授業目標をはっきりと理解し、その目標を達成するために主体的に学習活動をおこなっていく授業。また、授業の終わりに、その授業を振り返って、何を学んだのか、何ができたのかを自分の言葉で語れるような授業。
② 魅力的な授業をおこなう。魅力的な授業とは、子供が授業目標に興味関心を持ち、意欲を持って学びたいと感じる授業。さらに、その授業で学んだことが、子供の日常生活と繋がり、教室で学んだことが、子供自身の社会や世界で生かせることを実感できる授業。
③ 全ての学びは、子供たちの興味関心から始まるため、いかにして、子供たちの興味関心を呼び起こすかについて工夫する。ICTの活用や、写真や図などを活用し、視覚に訴える工夫をおこなうことで、子供の瞬間的な理解を促し、これから学ぶことへの興味関心を呼び起こす。
④ 子供たちの驚きを大切にする授業をおこなう。毎回の授業で、どこかで、子供たちが何かを発見し、何かに気づいて驚くという瞬間を大切にする。人は驚きから、興味を持ったり、関心を持ったりする。驚きを重視した授業を毎回行うことで、子供たちの心に残る学びを展開していく。
子供たちを対話的に学ばせるためには:
① 3つの環境を整備する。一つ目は話しやすい人間関係を作ること。共感的な人間関係があれば、話しやすくなり、たとえ対立する意見でも交換しやすくなる。二つ目は、子供たちが興味を持って話しやすい課題を提供すること。子供たち自身が課題を見つけることが理想的であるが、いずれにしても、話したくなる課題が不可欠である。三つ目は、対話の相手を多様化すること。クラスメートだけではなく、時には教員と、時には地域の人と、というように、多様な人との対話を大切にする。
② 対話の根本は、自分にないものを他者から学ぶこと。多様な意見に触れて、自分に無かった視点や思いに触れて、その上で、自分の考えを高めていく。そこで、例えば、ジグソー方式の学習活動を取り入れ、子供たちそれぞれが、異なる情報を持ち寄って、その情報を共有しながら、課題を解決するという実践を行う。
深い学びのためには:
① 問題発見と問題解決の過程を重視する。子供が意欲をもって課題を発見し、それを解決するプロセスを大切にする。そのために、見通しを持って学び、学んだ後に振り返る活動をすることが重要。課題を見つけるためには、興味関心が必要であり、課題を解決するには、思考・判断・表現が必要。こうした学びの過程を、見通すことと振り返ることで、子供が自分自身の学びとして経験していくことが必要だと考える。
② 学びたいことを自ら見つけて、自ら学ぶ。知識の伝授から、課題発見・課題解決の学びへと、子供の学び方を変えていく。学ぶべきものが一方的に提示され、言われた通りに学ぶという学び方から、子供たちが興味関心に基づいて自ら課題を発見して、その課題を仲間と情報交換をしながら協働して解決していくという学習のプロセスを重視する。
(補足:+全体として。)
以上を踏まえて、「主体的・対話的で深い学び」によって、言語能力を鍛える:
言語能力を鍛えることで、思考力が向上する。
思考力があがれば、メタ認知=自分を第三者的な視点で見ることができるため、視野を常に 広く持ち、いろいろな可能性について、客観的かつ冷静に選択・判断することができる。
具体的に、どのようにして、それぞれの学びを促していけばよいのかを記載していきました。
文部科学省は、「深い学び」が重要であると述べていましたが、私個人としては、まずは、「主体的な学び」が一番重要だと考えています。
「主体的な学び」は、上記のサンプルにも記載したように、子供の意欲・興味・関心があってこそです。
従って、「主体的な学び」が無い以上、「対話的な学び」も「深い学び」も成し得ません。
・・・・と、ここまで述べていくと、
「万能な」の意味が理解していただけたかと思います。
昨年の、全国の面接試験において聞かれた質問を見てみると、
・教師になってどのような教育をしたいですか?
・どのような授業をおこないますか?
・どのような教師になりたいですか?
・子供が主体的に学ぶために、どのような手立て・工夫をおこないますか?
・これからの教育に求められていることは何だと思いますか?
・教師に必要な力とは何ですか?
・生きる力を身に付けさせるために(伸ばすために)、どのように取り組みますか?
・言語活動の充実について、あなたならどのような指導をおこないますか?
・確かな学力を身に付けさせるためには、どうしたらよいと思いますか?
等がありました。
「主体的・対話的で深い学び」を理解して、サンプルのような、自分の核を持っておくと、上記のどの質問が来ても、答えられるようになります。
もちろん、全ての質問で「主体的・対話的で深い学び」に関連したことを言うと、面接官からすれば、「こいつ、これ以外何も学んでいないな。」、「くどいな。」と呆れられてしまいますが・・・
あくまで、どんな教育をしたいかという領域において、想いの核の一つとして、もっておくといいのではないかと思います。
使いまわす、という意味で、あまり感じはよくない表現ですが、
「コピペは恥だが、役に立つ。」
だと思います!
ちょっと古かったですかね(笑)
では、また7の付く日に!!
教採塾
川上貴裕